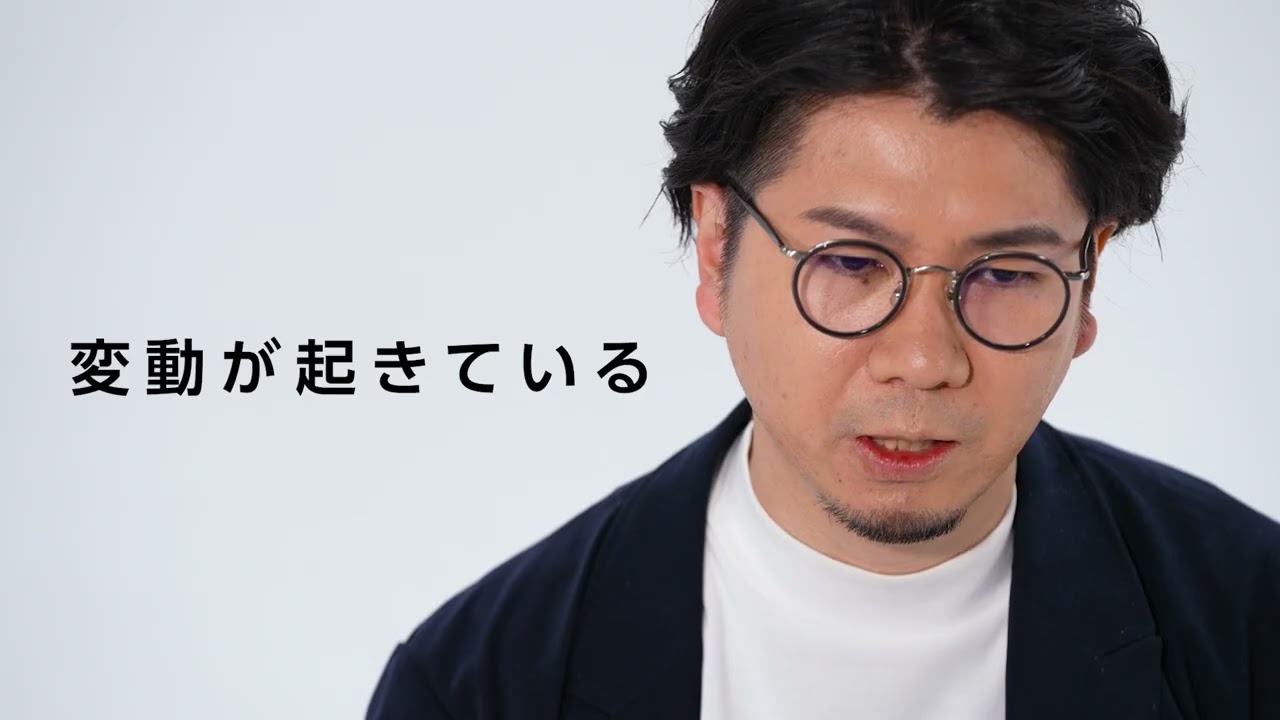
BIMの道は、自分たちで作る。
BIMマネージャー
高梨 裕気
- 建設業の人手不足に立ち向かう。
-
今、建設業界全体では生産年齢人口が減少して、とくに現場に近い職種では人材不足が深刻になっています。そうした中で、私はBIM(Building Information Modeling)の活用が「切り札」になり得ると考えています。
BIMを導入することで、作業の手戻りやムダを減らし、現場の負担を軽くすることができます。限られた人手を“前工程”に集中させることで、全体の生産性を高めることができ、少ない人数でも質の高い現場をつくれる。私はそう信じています。
- BIMをどう使いこなしていくのか?
-
従来の図面は、いわば「ただの線」にすぎませんでした。でも、BIMで作るモデルはまったく違います。たとえば、仕上げ材や使用する建材、温度管理に関する情報など、さまざまなデータをBIMモデルに盛り込むことができます。
こうした情報付きのモデルを次の工程に引き継ぐことで、職種の異なる人たちとのコミュニケーションが一気にスムーズになります。私は、BIMをきちんと活用することで、設計、施工管理といった各フェーズをつなぐ“共通言語”として機能する。そんな可能性を実感しています。
ただし、BIMを導入すればすぐに成果が出るというものではありません。まず必要なのは、今の業務そのものを見直すこと。その見直しの深さこそが、BIMを本当に活かせるかどうかを左右する。私はそう感じています。

- BIMは「ただのツール」ではない。
-
設計図が手描きからCADへ移行したときは、たしかに効率化は進みましたが、業務の仕組み自体は大きく変わりませんでした。でも、CADからBIMへの移行は、働き方そのものが変わるほどの大きなインパクトがあります。単なる「描き方の進化」ではないんです。
実際、私たちの現場でも、部門ごとの業務の分断が見直され、部門間の連携がより早い段階で可能になりました。たとえば、断熱パネルや鉄骨の図面も、それぞれの協力会社が作成したデータをそのまま3Dモデルに反映し、各社の図面が一つに集約されることで、整合確認が格段に効率化されています。
これまでのように、複数の図面を突き合わせて確認する必要がなくなり、BIMを使えば干渉不具合も一目で把握でき、事前に施工図を修正して現場のトラブルも未然に防げます。全員が同じモデルを見ることで認識のズレも減り、コミュニケーションもよりスムーズになります。
私は、BIMは単なる図面ツールではなく、組織や働き方そのものを変える力を持っていると感じています。
- BIMに正解はない。だから、自分たちで答えをつくる。
-
大手ゼネコンでも、BIMを完璧に使いこなしているとは言い切れません。他社のやり方をそのまま自社に当てはめても、環境や人材が違えばうまくいかない。だからこそ、私は三和建設に合ったBIMの使い方を、自分たちの手で育てていく必要があると思っています。
大手企業は資本力を背景に、先端技術への取り組みを進めています。それに対して中小企業がそれをないがしろにしてしまえば、差は開く一方です。だからこそ、私たちも10年後を見据えて、BIMやデジタルの分野に積極的に取り組むべきだと考えています。
BIM自体決まりきった道はないと思ってます。今は、自分でレールを作っているっていう感覚です。

- BIMが変える、建設プロセスの本質。
-
BIMを導入することは、単なる作業の効率化ではありません。業務プロセス自体を見直すきっかけになる。今まで存在しなかった仕事が生まれる可能性もあれば、逆に削減できる仕事もある。私は、BIMが自分たちの仕事の中身をもう一度深く考える機会を与えてくれる存在だと感じています。
